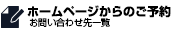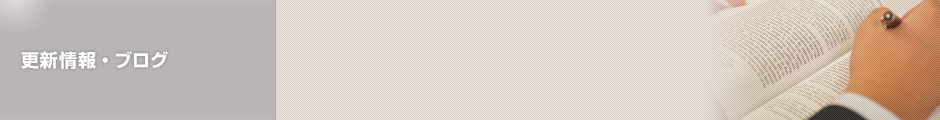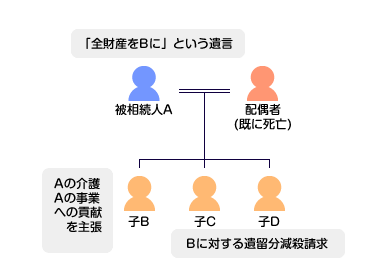
事務所に来られた方から日々様々なご相談をいただきますが、最近相続関連のご相談が多いと感じています。
相続分野は、様々な制度が混在しており、制度間の関係性を把握するのが難しい分野です。
今回は遺言と遺留分と寄与分の関係について取り上げてみたいと思います。
(事例)
亡くなったAにはB、C、Dという子がいました。Aの生前、BがAの仕事を手伝い、Aが病床に伏してからはBがAを献身的に介護していたので、AがBの功績を認め「全財産をBに譲る」という遺言を書きました。
(遺言と遺留分の関係)
このような状況でCとDはBに対して何か言えることがあるでしょうか。
…子は親の遺産に関し遺留分を持っています。遺留分は遺言によっても奪うことができません。CとDはAの子ですのでAの遺産に関し遺留分を持っており、CとDは全財産を遺贈されたBに対して遺留分減殺請求権を行使できます。
(遺留分と寄与分の関係)
これに対して、Bは、生前Aの仕事も手伝わず介護もしていないCとDに遺産を分けることに納得がいかず、CとDの遺留分減殺請求に応じずにいたところ、C及びDから遺留分減殺請求の訴訟を提起されました。
この訴訟において、Bは、「自分の働きによってAの財産を増やしたり、維持したりできたんだから、その部分については遺留分など認められない」と反論することができるでしょうか。
…現在の通説、裁判例(東京高決平成3年7月30日判タ565)上、そのような反論はできません。
Bの反論は、法律上「寄与分」と呼ばれるものです。寄与分が認められる場合、相続財産から寄与分の額を控除して算定した額を相続財産とします。
もっとも、民法上、遺留分の算定の基礎となる財産は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価格に生前に被相続人が贈与した(一定の)財産の価格を加えたものとされています。すなわち、遺留分の算定の基礎から寄与分を控除することは民法に定められていないのです。また、寄与分は、相続人の間で協議が整わない場合、家庭裁判所が審判で決めるものだと民法で規定されており、訴訟で反論することが予定されていません。
したがって、BはCとDから起こされている遺留分減殺請求訴訟の中で、Aの遺産の中からBの寄与分を控除した額を遺留分の基礎にしてほしいと主張することができないのです。
いかがでしょうか。3つの制度があるだけで結構複雑ですが、さらにこれに認知、養子縁組等(誰が遺留分権利者なのか)、特別受益等が関わってくるともっと複雑になります。親族関係が入り組んでいる場合の相続は事前に専門家の意見を聞くことをお勧めします。