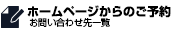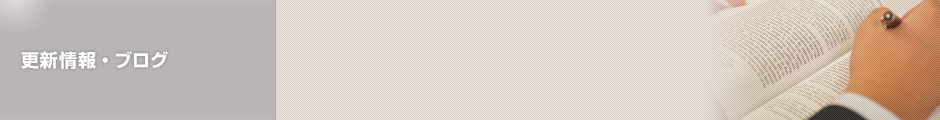弁護士の最所です。
先日、最高裁判所が、民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は、遅くとも平成13年7月当時(被相続人の死亡時)憲法14条1項に違反していたと判断しました(平成24年(ク)第984号、第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成25年9月4日 大法廷決定)。
法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子(嫡出子)の2分の1と定めることが、合理的理由のない差別的取扱いにあたるかが争点になりました。
決定では、昭和22年の民法改正当時の社会状況(当時非嫡出子に相続分を認めない諸外国の立法例が存在していた状況や相続財産は嫡出の子孫に承継させたいという気風など)からの変化や、平成7年に合憲決定が出された以降の諸外国の状況(相続に関する差別を廃止する立法が、平成10年にドイツで、平成13年にはフランスでなされ、嫡出子と非嫡出子の相続分に差異を設けている国は、欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況にあることなど。)の変化、国連関連組織から懸念や法改正の勧告を受けていたという事情、そして、社会状況の変化に伴い、非嫡出子と嫡出子を区別する法制に変化が生じているなどの事情を詳細に検討した上で、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許さ」ないと判断しました。
相続分をめぐる嫡出子と非嫡出子との紛争には、被相続人の二つの「家族」間の争いという実態があるのが通常だと思います。
嫡出子と非嫡出子の立場を、仮に想定し、双方の立場の本音を想像してみます。
嫡出子の側からすれば、「親が浮気をして外に作った『愛人たち』に、なぜ遺産を渡さなければいけないのか、むしろ、家庭を壊した連中に対して、損害賠償が認められてしかるべきでではないか。」という感情をもつでしょうし、逆に、非嫡出子の側からすれば、「長年、親を放置しておきながら、亡くなった途端に財産をよこせなどとは理解できない。とうの昔に実際の婚姻関係は崩壊しているし、自分たちは、相手方が離婚に合意しないから、法律上の家族となれなかっただけだ。自分が生まれてからの親との関わりは、自分の方が密接で、自分達の方が、正当な家族だ」といった感情を持つことは十分にありうると思います。
今回の決定を、非嫡出子を守るために嫡出子の権利を制限したと誤解されている方もいらっしゃるとは思いますが、今回の決定は、あくまでも、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていると判断し、法定相続分の区別をすべきではないと判断したに過ぎません。
今回の決定によっても、被相続人の生活実態から、寄与分、特別受益による調整は可能ですし、そもそも被相続人の遺言があれば、遺留分の点を除いて、遺言が優先されることになりますので、直ちに、嫡出子の権利が制限されるという関係には立ちません。
もっとも、今回の決定によって、嫡出子の側が不利益を受けるケースとしては、「親の死後、突然、子どもと称する人物が現れ、法定相続分に従った遺産分割を求めたり、遺留分に相当する金員の支払いを求めてきた」というような場合が想定されますが、この場合にも、非嫡出子と嫡出子の法定相続分を同じとすることに、はたしてコンセンサスが得られるかは、なかなか難しい問題だと思います。
今回の決定では、岡部喜代子裁判官の補足意見(注:PDFファイルへのリンクになります。引用部分はp18以降)で、我が国の一つの家族像に関して、適確な説明がなされていましたので、引用致します(同裁判官も違憲の結論に賛成しています。)。
夫婦及びその間の子を含む婚姻共同体の保護という考え方の実質上の根拠として,婚姻期間中に婚姻当事者が得た財産は実質的には婚姻共同体の財産であって本来その中に在る嫡出子に承継されていくべきものであるという見解が存在する。
確かに,夫婦は婚姻共同体を維持するために働き,婚姻共同体を維持するために協力するのであり(夫婦については法的な協力扶助義務がある。),その協力は長期にわたる不断の努力を必要とするものといえる。
社会的事実としても,多くの場合,夫婦は互いに,生計を維持するために働き,家事を負担し,親戚付き合いや近所付き合いを行うほか様々な雑事をこなし,あるいは,長期間の肉体的,経済的負担を伴う育児を行い,高齢となった親その他の親族の面倒を見ることになる場合もある。
嫡出子はこの夫婦の協力により扶養され養育されて成長し,そして子自身も夫婦間の協力と性質・程度は異なるものの事実上これらに協力するのが通常であろう。
これが,基本的に我が国の一つの家族像として考えられてきたものであり,こうした家族像を基盤として,法律婚を尊重する意識が広く共有されてきたものということができるであろう。
平成7年大法廷決定が対象とした相続の開始時点である昭和63年当時においては,上記のような家族像が広く浸透し,本件規定の合理性を支えていたものと思われるが,現在においても,上記のような家族像はなお一定程度浸透しているものと思われ,そのような状況の下において,婚姻共同体の構成員が,そこに属さない嫡出でない子の相続分を上記構成員である嫡出子と同等とすることに否定的な感情を抱くことも,理解できるところである。
(岡部喜代子裁判官補足意見の一部)
最高裁判所の判断が出てしまった以上、早期に、民法900条4号ただし書の規定が見直されることになると思いますが、最高裁の判断の是非については、ひとまずおくとしても、相続人間での無用な紛争を避けるためにも、事前に専門家に相談した上で、遺言書を作成されることをお勧め致します。