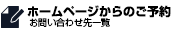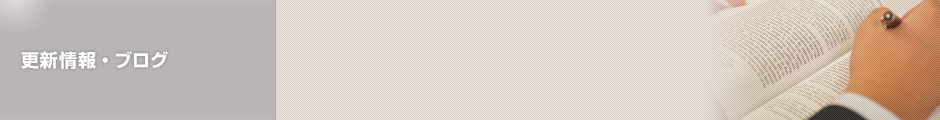弁護士の最所です。
民法750条は、「夫婦は」「夫又は妻の氏を称する。」と規定しています。その為、「夫婦」が別々の氏を称することは、現行法の下では認められていません。
また、民法733条は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定していて、女性だけが、離婚後の再婚を6か月間禁止されています。
これらの規定が、憲法に違反するかが争われている2つの裁判について、最高裁判所は18日、大法廷による審理を行うことを決めました。
・夫婦別姓と待婚期間の問題に対し、初めて最高裁判所の憲法判断が下される見通し
最高裁判所には、5人の裁判官で構成する3つの小法廷と、最高裁判所長官を含む15人の裁判官全員で構成する大法廷とがあります。このうち、法律が憲法に適合するかしないかを判断する際には、大法廷で審理及び裁判を行わなければなりません。
最高裁判所が、敢えて大法廷での審理を行うと決めたことからすれば、これらの問題について、最高裁判所は、憲法判断を行うとの姿勢を示したことになるでしょう。
仮にこれらの問題について最高裁判所が憲法判断を行うとすれば、婚外子の相続格差に関する最高裁違憲決定に続き、婚姻制度や家族の在り方に関わる重要な判断がまた一つ下されることになります。
現状の報道されている限られた情報を基にしたものではありますが、私の最高裁判所の判断についての予想を述べさせて頂きます。
・夫婦別姓を認めない規定に対する違憲判断の可能性
民法750条は、「夫婦は」「夫又は妻の氏を称する。」と規定しており、「夫婦」である以上、別姓は認められていません。
今回の裁判では、夫婦別姓を認めていない民法の規定が、個人の自由を過度に制約するものとして、違憲ではないかということが問題とされています。
法律の制定は、国民の代表機関である国会の役割です。このことは憲法41条において、明確に定められています。国会とは言うまでもなく、選挙によって選ばれた議員によって構成される機関です。
国会は、国民の多種多様な意見を汲み取って、審議し、その過程においてある種の妥協をし、最終的に議決を行うことで、法律を作り上げる機関として予定されています。
憲法が、国会に法律を作る権限を与えている以上、国会がいかなる内容の法律を作成するかについては、国会に裁量があります。また、国会が、選挙によって選ばれた議員によって構成される機関である以上、国会の意思が、国民の多数派の意思を反映したものになることはやむを得ません。
しかしながら、多数派の意思が、少数派の権利を不当に害するようなものであれば、そのような法律は憲法に違反するものとして、違憲無効とされなければなりません。そのための権限を、憲法は最高裁判所に与えています。
そこで、今回問題となっている民法750条の規定が、少数派の権利を不当に害しているものと言えるのかについて、検討します。
夫婦の氏の取り扱いをどのようなものにするかということは、婚姻制度の制度設計の問題と直結せざるを得ません。
婚姻制度が国家における「制度」である以上、制度設計上、国民全体の多種多様な意見をすべて汲み取って制度に反映させるのは実際上不可能です。
国家における制度設計を行う以上、多数派の意見を反映した制度、言い換えれば、ある種の社会的慣習に従った制度設計になるのはやむを得ないと言えるでしょう。
夫婦別姓を希望する人々が少数派ではあることは、各種の世論調査からも見て取れます。(ex.家族の法制に関する世論調査)。
では、現行民法の夫婦が同姓でなければならないとする「制度」が、少数派である人々の権利を不当に害していると言えるでしょうか。
確かに、別姓を希望する人々にとっては、婚姻による「恩恵」を受けることはできなくはなりますが、民法750条は、法律婚をする場合には、姓を同一にしなければならないという点を規定しているに止まっています。
民法750条は、別姓での法律婚を禁止するに止まり、別姓を維持するための事実婚を禁止するまでのものではありません。
仮に、法律婚と事実婚との間に、取り扱いの差違が著しいものであれば、違憲と判断されなければならないという方向に流れるでしょう。
しかしながら、社会保障等の点において、事実婚と法律婚との間の差違が少なくなってきているという現在の社会情勢からすると、必ずしも、少数派である人々の権利を「不当に」害しているとまでは言えないのではないかと思います。もちろん、差違がないという趣旨ではありません。
婚姻は個人の自由に属する領域の問題であるとも言えますが、国家における「制度」であるという側面は否定できません。仮に、婚姻が、個人の自由領域の問題であるとするのであれば、夫婦別姓だけではなく、例えば同性同士の結婚についても認めることが、論理的となるでしょう。
しかしながら、夫婦別姓論者の人が、同性婚についても肯定的かというと必ずしもそうではないように思えます。それは、同性婚の夫婦を制度上の夫婦としては取り扱うべきではないとの社会慣習が存在し、無意識的に、そのような社会慣習に従っているのではないかと思います。
確かに、婚姻制度をどのような形とすべきかという点については、時代の変化に伴って、様々な考え方が生じてきますので、国民の間で様々な議論がなされなければならない問題であると思います。
しかしながら、国民の間での様々な議論をしていかなければならない問題である以上、婚姻制度自体の根本的な変更は、裁判所による判断ではなく、選挙によって選ばれた議員によって構成される国会の立法を通じて実現すべき問題であるというべきです。
現状においては、各種の世論調査を見ても、夫婦別姓を選択できるようにすべきであるという社会的なコンセンサスが醸成されたとまでは言えません。また、民法の規定自体は、夫と妻の姓のいずれでも選択できるとされている以上、男女差別にあたるという考え方も難しいのではないかと思います。
私は、夫婦別姓を認めていない民法の規定について、違憲の判断がなされる可能性は低いのではないかと考えています。
・待婚期間の規定に違憲判断がされる可能性は
では、待婚規定の点は、どうでしょうか。
民法733条は、女性は前婚の解消の日から6か月(いわゆる待婚期間)を経過した後でなければ、再婚をすることができないと定めており、期間中、女性の結婚する権利が制限されています。
この規定は、父性推定の重複を防止する為の規定とされています。しかし、民法は懐胎期間を200日から300日と想定し、婚姻成立の日から200日を経過した後、又は、婚姻が解消されてから300日以内に生まれた子については、婚姻中に懐胎したものと推定しています。
この規定からしても、父性の推定が重なる期間は最大100日でしかありません。すなわち、父性推定の重複を防止する為に、必要な禁止期間は、100日間で足りるはずです。この点に関する指摘は、かなり以前からもなされていました。
また、この規定を、父子関係の確定を困難にすることを避ける為の目的であると広く捉る見解もあります。
仮に、民法の規定を法律上の父性推定の重複を避ける目的に止まらないと考えたとしても、現在では、医療の発達により、妊娠しているか否かは、着床後早期に判断することが可能ですし、また、民法733条の規定による事実上の効果は、再婚の届出を受理しないということに止まり、事実上の再婚(内縁)を禁止するものではないことからすれば、待婚禁止の規定によって、父子関係の確定が困難となるという事態が生じることを防ぐことは、全く期待することはできません。
すなわち、そもそも、法律による規制をしなければならない合理性それ自体が、相当疑わしいと言わざるを得ない状況になっているのです。
規制に合理性がなく、また、女性のみに、合理性のない待婚期間を設けて不利益を課している点について、違憲であるとの判断がなされる可能性は、相当程度あるのではないかと考えています。
・立法の目的と社会状況の変化が判断の鍵となる
以上の2つの裁判について、私の考えを書かせていただきましたが、結論が分かれたポイントは、立法目的と、社会状況の変化の関係にあると考えています。
昨今の夫婦別姓を巡る状況からすると、近い将来に夫婦別姓についての社会的コンセンサスができ、社会的慣習が変化したと言える状態になる可能性はあります。その場合、社会慣習の変化に伴い、選挙によって選ばれた国民の代表者によって構成される国会の議決によって法律改正がなされることになるでしょう。
一方、待婚期間については、生殖医療の発達という明らかな社会状況に変化が生じており、また、女性にのみ制限を課していることからも、最高裁判所による違憲判断を期待することができる問題なのではないかと思われます。
(本件記事は、弊所所属弁護士松尾雄司と共同執筆致しました。)